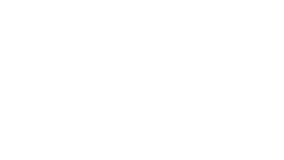財団法人ルンデ設立への道
この記事は、一般財団法人ルンデの村林基彦が、Facebookの個人ページに2017年10月19日から、2017年11月8日にかけて書いた文章に加筆修正したものです。
2025年2月13日、ルンデ創立者の鈴木詢の一周忌に、登場人物略歴を追加して掲載します。
2025年2月13日、ルンデ創立者の鈴木詢の一周忌に、登場人物略歴を追加して掲載します。
その.1 ちゅうしんコンサート
何故、スタッフでも親族でもなかった村林がルンデの名を継いだのか、当然反発もあるんだろうな、、と思い経緯を書きます。
まず話は、2016年10月11日バロックアンサンブル「ストラディヴァリア」を聴きに行ったところに遡ります。
チェロ奏者の酒井淳さんが共演するということで、聴きに行きました。
客席は、どこか僕の知ってる宗次ホールの客席の雰囲気ではありませんでした。来日して名古屋に来ている演奏家の方がかなりいらっしゃいました所為かもしれません。
ダニエル・キュイエのヴァイオリンには「質」をこえた何かを感じ、アンサンブルも素敵で楽しく、時間の濃密さを感じるコンサートでした。
客席には見知った顔もチラホラ、、、そこでスタジオ・ルンデ主宰の鈴木詢さんに呼び止められました。
「あなたに、聞いてもらいたい話がある」と
急ぎではなかったので、後日、BreakCafeに来ていただけるということでその日は演奏会を充分たのしみ、コンサートの後は酒井くんと酒井くんのご家族のみなさんと近況報告をしました。弟のタカシ君が医者になっていたのはビックリしました。
穏やかに晴れた、10月29日の午前中、鈴木詢さんはBreakCafeにいらっしゃいました。
お話のメインは「ちゅうしんコンサート」の今後について。折しもデイブレイクフレーバーが中日信用金庫と取引を始めるかどうかというタイミングも重なりました。
秋に行われる「ちゅうしんコンサート」は国内海外とわず旬の演奏家を招き、無料でお昼に2回(2025年2月現在は1回)おこなわれるコンサートです。鈴木詢さんは、あと数年したら法人を閉じてコンサートのマネージメントからも身をひくつもりだ、ただ、中日信用金庫としては「ちゅうしんコンサート」を続けていきたいので、誰か引き継げる人はいないのかというリクエストがある、と。
今付き合いのある音楽事務所は紹介するし、新たに自分で開拓してもよいから、やってみないかと。
流石に、室内楽を聴きにいく機会も減っていて「今」名実共に充実している、演奏家をすぐに選べるかといわれたら自信はありませんでした。お願いしたことは、経験をつむまで暫く一緒にやってくださいということ、それであれば喜んでお手伝いしたいと伝えました。
第36回ちゅうしんコンサート
≪ いま望みうる最高のデュオ 山崎伸子&小菅優 デュオ・コンサート ≫
翌月、11月25日、中日信用金庫本店の2階で行われました。ここで、今につながる一筋の道が見えたような気がしました。この時、山崎伸子さんの腱鞘炎は予後良好でしたが、無理をしたくないとのことで小菅優さんのピアノソロを聴いたのも大きかったと思います。
まず話は、2016年10月11日バロックアンサンブル「ストラディヴァリア」を聴きに行ったところに遡ります。
チェロ奏者の酒井淳さんが共演するということで、聴きに行きました。
客席は、どこか僕の知ってる宗次ホールの客席の雰囲気ではありませんでした。来日して名古屋に来ている演奏家の方がかなりいらっしゃいました所為かもしれません。
ダニエル・キュイエのヴァイオリンには「質」をこえた何かを感じ、アンサンブルも素敵で楽しく、時間の濃密さを感じるコンサートでした。
客席には見知った顔もチラホラ、、、そこでスタジオ・ルンデ主宰の鈴木詢さんに呼び止められました。
「あなたに、聞いてもらいたい話がある」と
急ぎではなかったので、後日、BreakCafeに来ていただけるということでその日は演奏会を充分たのしみ、コンサートの後は酒井くんと酒井くんのご家族のみなさんと近況報告をしました。弟のタカシ君が医者になっていたのはビックリしました。
穏やかに晴れた、10月29日の午前中、鈴木詢さんはBreakCafeにいらっしゃいました。
お話のメインは「ちゅうしんコンサート」の今後について。折しもデイブレイクフレーバーが中日信用金庫と取引を始めるかどうかというタイミングも重なりました。
秋に行われる「ちゅうしんコンサート」は国内海外とわず旬の演奏家を招き、無料でお昼に2回(2025年2月現在は1回)おこなわれるコンサートです。鈴木詢さんは、あと数年したら法人を閉じてコンサートのマネージメントからも身をひくつもりだ、ただ、中日信用金庫としては「ちゅうしんコンサート」を続けていきたいので、誰か引き継げる人はいないのかというリクエストがある、と。
今付き合いのある音楽事務所は紹介するし、新たに自分で開拓してもよいから、やってみないかと。
流石に、室内楽を聴きにいく機会も減っていて「今」名実共に充実している、演奏家をすぐに選べるかといわれたら自信はありませんでした。お願いしたことは、経験をつむまで暫く一緒にやってくださいということ、それであれば喜んでお手伝いしたいと伝えました。
第36回ちゅうしんコンサート
≪ いま望みうる最高のデュオ 山崎伸子&小菅優 デュオ・コンサート ≫
翌月、11月25日、中日信用金庫本店の2階で行われました。ここで、今につながる一筋の道が見えたような気がしました。この時、山崎伸子さんの腱鞘炎は予後良好でしたが、無理をしたくないとのことで小菅優さんのピアノソロを聴いたのも大きかったと思います。
その.2 正文館本店
話はさらに過去に遡ります。まだ守山区小幡に住んでいた頃だから、19歳(神戸の震災があり、地下鉄サリン事件が起きた頃です)の頃、名古屋市東区の東片端の正文館書店でアルバイトをし始めました。一度は断られたけど、リニューアルオープンで思った以上にアルバイトの人数がいるということで、復活採用となりました。
なぜ、本屋のバイトが、財団法人ルンデの話しにつながるのかというのは、この正文館で出会った人達がいなければ、「今、ココ」に辿り着かないのです。
後に、名古屋市民吹奏楽団で短い期間だけど一緒に演奏活動をした、トランペット吹きのお姉様。当時、団を立ち上げる正にその時で、高校で吹奏楽部でサックスを吹いていましたという話をしたら、名古屋市民吹奏楽団に誘われました。当時の練習場所が遠くて練習に行きづらい場所だったのでお断りしましたが、その時、大人になっても吹奏楽を楽しむ場所があるんだということを知りました。
「カフェ・コンセール・エルム」でシャンソン歌手として活躍されている馬路さん。絵本のコーナーでちょっとしたお話するのが楽しくて、たくさん児童書を手に取る機会をいただきました。
名古屋在住の歴史作家のお嬢さんもいらっしゃいましたね。当時のパート、バイト仲間は「独特」な人達が多くて、幅広い年代の方達とお話する機会も増え、とても楽しかった記憶があります。
そう、その中に現役の作家さんもいたんです。
「綾辻行人、我孫子武丸、歌野晶午、有栖川有栖、貫井徳郎、島田荘司、天藤真、泡坂妻夫、北村薫、加納朋子、塩野七生、隆慶一郎、嵩峰龍二、竹河聖、今日泊亜蘭、梶尾真治、小野不由美」etc..
当時、よく読んでいた(本を買っていた)作家さんを思い出してみました。圧倒的に「ミステリ」ばかりです。アルバイトの給料で本の購入代金を精算を出来るシステムがあったのも高じて、ほとんどは本代に消えていました。
これだけ偏った読み方をしていたので、ミステリに関しては社員さんよりも情報が豊かに手元にありました。当時「京極夏彦」や「森博嗣」のデビュー作の講談社ノベルズの注文数を迷う担当社員さんに倍の冊数を言って「?」を頭の上にちらつかせながらもアルバイトの勘を信じてくれて注文してくれたのは単純に嬉しかったです。
そう、作家さん。当時、富士見ファンタジア文庫や青心社で本格ファンタジーを執筆していた「神江京」という作家さんが同じアルバイト仲間でした。
よく、ミステリやファンタジー、アニメやゲームの話をした覚えがあります。
そんなある日、彼女から「オヤジの仕事でコンサートの記録ビデオ撮る仕事があるけど、アルバイトしないか?」と。大学の講義が午前中で終わる日だったこともあり、早めにいってリハーサルで撮影の練習しても大丈夫ということだったのでそのアルバイトを受けました。
「ルンデあしながクラブ」主催のコンサートでした。
このコンサートではじめて、チェリストの酒井淳さんと出会いました。聞くと同じ年齢。ビデオカメラをまわしながらだけど衝撃をうけました。音楽って素敵だということと、類い希なる才能が目の前にあって、それがほぼ同じ時間を重ねてきた笑顔が気持ちのよい男の子だということ。
財団法人ルンデの理事を務めていただく、パイプオルガン奏者の吉田文さんとともに酒井淳さんは「ルンデあしながクラブ」を象徴するアーティストです。
本屋のアルバイトから、スタジオ・ルンデ主宰の鈴木詢さんに出会うまで、、、これが誰かの気まぐれなんでしょうかね。
大学の講義で隣に座ってた子がアルバイト情報誌をまわしてくれなかったら?と思うと、背筋が冷えます。
なぜ、本屋のバイトが、財団法人ルンデの話しにつながるのかというのは、この正文館で出会った人達がいなければ、「今、ココ」に辿り着かないのです。
後に、名古屋市民吹奏楽団で短い期間だけど一緒に演奏活動をした、トランペット吹きのお姉様。当時、団を立ち上げる正にその時で、高校で吹奏楽部でサックスを吹いていましたという話をしたら、名古屋市民吹奏楽団に誘われました。当時の練習場所が遠くて練習に行きづらい場所だったのでお断りしましたが、その時、大人になっても吹奏楽を楽しむ場所があるんだということを知りました。
「カフェ・コンセール・エルム」でシャンソン歌手として活躍されている馬路さん。絵本のコーナーでちょっとしたお話するのが楽しくて、たくさん児童書を手に取る機会をいただきました。
名古屋在住の歴史作家のお嬢さんもいらっしゃいましたね。当時のパート、バイト仲間は「独特」な人達が多くて、幅広い年代の方達とお話する機会も増え、とても楽しかった記憶があります。
そう、その中に現役の作家さんもいたんです。
「綾辻行人、我孫子武丸、歌野晶午、有栖川有栖、貫井徳郎、島田荘司、天藤真、泡坂妻夫、北村薫、加納朋子、塩野七生、隆慶一郎、嵩峰龍二、竹河聖、今日泊亜蘭、梶尾真治、小野不由美」etc..
当時、よく読んでいた(本を買っていた)作家さんを思い出してみました。圧倒的に「ミステリ」ばかりです。アルバイトの給料で本の購入代金を精算を出来るシステムがあったのも高じて、ほとんどは本代に消えていました。
これだけ偏った読み方をしていたので、ミステリに関しては社員さんよりも情報が豊かに手元にありました。当時「京極夏彦」や「森博嗣」のデビュー作の講談社ノベルズの注文数を迷う担当社員さんに倍の冊数を言って「?」を頭の上にちらつかせながらもアルバイトの勘を信じてくれて注文してくれたのは単純に嬉しかったです。
そう、作家さん。当時、富士見ファンタジア文庫や青心社で本格ファンタジーを執筆していた「神江京」という作家さんが同じアルバイト仲間でした。
よく、ミステリやファンタジー、アニメやゲームの話をした覚えがあります。
そんなある日、彼女から「オヤジの仕事でコンサートの記録ビデオ撮る仕事があるけど、アルバイトしないか?」と。大学の講義が午前中で終わる日だったこともあり、早めにいってリハーサルで撮影の練習しても大丈夫ということだったのでそのアルバイトを受けました。
「ルンデあしながクラブ」主催のコンサートでした。
このコンサートではじめて、チェリストの酒井淳さんと出会いました。聞くと同じ年齢。ビデオカメラをまわしながらだけど衝撃をうけました。音楽って素敵だということと、類い希なる才能が目の前にあって、それがほぼ同じ時間を重ねてきた笑顔が気持ちのよい男の子だということ。
財団法人ルンデの理事を務めていただく、パイプオルガン奏者の吉田文さんとともに酒井淳さんは「ルンデあしながクラブ」を象徴するアーティストです。
本屋のアルバイトから、スタジオ・ルンデ主宰の鈴木詢さんに出会うまで、、、これが誰かの気まぐれなんでしょうかね。
大学の講義で隣に座ってた子がアルバイト情報誌をまわしてくれなかったら?と思うと、背筋が冷えます。
その.3 《Studio RUNDE》
記録ビデオ撮影の時に、今度は《Studio RUNDE》でコンサートするから聴きに来てねと酒井淳さんから誘われました。それがルンデの客席デビューです。
1997年2月16日
「イリヤ・カーラー&酒井 淳〜デュオ」
これが室内楽なんだと納得させられ、形容できない質がそこにはありました。空間が音楽で変容していく体験はそれまで感じたモノが儚く崩れていくそれほどの衝撃でした。
1997年5月24日、26日(電気文化会館)
「The BARTÓK Quartet in NAGOYA,1997」
モーツァルト、バルトーク、チャイコフスキー、ハイドン、ショスタコーヴィチの弦楽四重奏、シューベルトの弦楽五重奏を二夜体験する。弦楽四重奏に対するとらえ方が変わった2日間。
1997年8月30日
「アポロン弦楽四重奏団&田中美千子」
スメタナ、ブラームス、ダヴィド・バラクリシュナン、パット・メセニー、チック・コリア。
プログラム見たときに驚いた。チック・コリアのセニョールマウスをやるという。
この年の12月にゲイリー・バートンとデュオで来日した時に聴くことになるのだけど、まさか弦楽四重奏でこの曲と出会えるとは、、Jazz、Fusionを越えHardな室内楽曲に昇華していました。
一気に室内楽に対する接し方がかわりました。
1997年10月15日(芸術文化劇場)、21日(京都コンサートホール大ホール)
「吉田 文 パイプオルガン・リサイタル《女流作曲家によるオルガン作品集》」
1997年10月29日
「酒井 淳 無伴奏チェロ・リサイタル」
1997年11月2日、3日
「スザナ・ルージチコヴァー チェンバロ連続リサイタル」
1997年11月13日
「戸田 弥生〜ヴァイオリンリサイタル」
1997年12月18日
「加古 隆 "パリは燃えているか"」
この後、御喜美江、高橋悠治をはじめとするルンデ常連アーティストが続いていきさらに室内楽にのめりこんでいくのだけど、1997年に体験した空間が今日の自分の土台になっていることは確か。
1997年2月16日
「イリヤ・カーラー&酒井 淳〜デュオ」
これが室内楽なんだと納得させられ、形容できない質がそこにはありました。空間が音楽で変容していく体験はそれまで感じたモノが儚く崩れていくそれほどの衝撃でした。
1997年5月24日、26日(電気文化会館)
「The BARTÓK Quartet in NAGOYA,1997」
モーツァルト、バルトーク、チャイコフスキー、ハイドン、ショスタコーヴィチの弦楽四重奏、シューベルトの弦楽五重奏を二夜体験する。弦楽四重奏に対するとらえ方が変わった2日間。
1997年8月30日
「アポロン弦楽四重奏団&田中美千子」
スメタナ、ブラームス、ダヴィド・バラクリシュナン、パット・メセニー、チック・コリア。
プログラム見たときに驚いた。チック・コリアのセニョールマウスをやるという。
この年の12月にゲイリー・バートンとデュオで来日した時に聴くことになるのだけど、まさか弦楽四重奏でこの曲と出会えるとは、、Jazz、Fusionを越えHardな室内楽曲に昇華していました。
一気に室内楽に対する接し方がかわりました。
1997年10月15日(芸術文化劇場)、21日(京都コンサートホール大ホール)
「吉田 文 パイプオルガン・リサイタル《女流作曲家によるオルガン作品集》」
1997年10月29日
「酒井 淳 無伴奏チェロ・リサイタル」
1997年11月2日、3日
「スザナ・ルージチコヴァー チェンバロ連続リサイタル」
1997年11月13日
「戸田 弥生〜ヴァイオリンリサイタル」
1997年12月18日
「加古 隆 "パリは燃えているか"」
この後、御喜美江、高橋悠治をはじめとするルンデ常連アーティストが続いていきさらに室内楽にのめりこんでいくのだけど、1997年に体験した空間が今日の自分の土台になっていることは確か。
その.4 壁はがし
2007年の「ルンデさよならコンサート」のラインナップ「御喜美江& G. F. シェンク」「戸田弥生」「山崎伸子&若林顕」「吉野直子」「小林道夫」それぞれの想い出は強烈なんだけど、御喜美江さんにサイン会の時に「またココで会いましょう」とポロリと口にしたときからもしかしたら「次のルンデ」が始まっていたのかと思うこともあります。
建物の解体の際に、ルンデの象徴であった「レンガの壁」をはがして記念に持っていてという同窓会的な集まりがありました。その時のレンガの欠片をキービジュアルとして使っています。
2017年、ルンデの例会が幕を閉じてから10年、しらかわホールの主催公演も終了し、演奏者主催のコンサートは数多くあれど、県外、国外から演奏家を招いて定期的に行われるコンサートは宗次ホール、各テレビ局、自治体系の主催コンサートのみとなり、寂しく感じていきました。
「ルンデの例会」で感じたワクワクや緊張感は、なかなか他の場所では味わえませんでした、、もしあんなコンサートにまた行けたらと日々願っていました。ホールもないので同じ事は出来ないとは思うけど、少しでも近づけたらよいなと、数多くの演奏を吸収したであろうレンガを眺めながら思っています。
建物の解体の際に、ルンデの象徴であった「レンガの壁」をはがして記念に持っていてという同窓会的な集まりがありました。その時のレンガの欠片をキービジュアルとして使っています。
2017年、ルンデの例会が幕を閉じてから10年、しらかわホールの主催公演も終了し、演奏者主催のコンサートは数多くあれど、県外、国外から演奏家を招いて定期的に行われるコンサートは宗次ホール、各テレビ局、自治体系の主催コンサートのみとなり、寂しく感じていきました。
「ルンデの例会」で感じたワクワクや緊張感は、なかなか他の場所では味わえませんでした、、もしあんなコンサートにまた行けたらと日々願っていました。ホールもないので同じ事は出来ないとは思うけど、少しでも近づけたらよいなと、数多くの演奏を吸収したであろうレンガを眺めながら思っています。
その.5 登場人物略歴
鈴木 詢(1935年11月8日-2024年2月13日)
エンジニアを志し名古屋大学工学部に入学後、ほぼ独学で音楽を学び、名古屋大学交響楽団、労音オーケストラ(現:名古屋市民管弦楽団)などでアマチュア・オーケストラ運動の草創期に多く関わる。クラリネットを演奏し指揮をすることも多く、その際に、山本直忠氏(山本直純氏の父)に指揮法と作曲について指導を受ける。名古屋大学卒業後、本格的に音楽を学ぶために国立音楽大学器楽科へ。在学中に「音楽と工学がわかる人材がいないか?」というヤマハからの要望で、電子オルガンの開発に協力をする。
同世代の岩城宏之、藤田玄播、兼田敏らとも管弦楽、吹奏楽の演奏、指揮、編曲、作曲等で親交を深める。
卒業後、エレクトーンを普及させるべく「ヤマハ音楽教室」の全国展開、演奏グレード、指導グレードシステムの設立に深くかかわり、多くのエレクトーン指導者、奏者を育てる。
1981年5月室内楽専用ホール《Studio RUNDE》を名古屋丸の内でスタート、名古屋音楽大学の電子オルガンコースで教鞭もとり二足のワラジを履き「そのまたワラジをつくる人」として独特の仕草で多くの演奏家、音楽愛好家より慕われる。
「自分でやれることはやる」をモットーに、いちはやくコンピューターを導入し、チラシ、プログラムの印刷、会報の発行等は事務所内で行う。インターネット黎明期よりWEBサイト「pippo-jp」を立ち上げ、ルンデの例会の案内だけではなく、近隣のコンサートホールの催し物情報や、俳句、エッセイ等の文学の発表の場として提供。
なお、この「pippo」というのは、最愛の孫のゆかりがルンデの事務所の扉が開くと鳴るベルの真似をして「ぴっぽ〜♪」ってよく口ずさんでいたことから、彼女の愛称が「ぴっぽちゃん」になり、ドメイン名になりました。
神江 京
作家、富士見ファンタジア文庫、青心社にて本格的ファンタジー文庫を数多く執筆。長女ゆかり出産後、執筆業を一時休業するも、2025年現在は、「コメントサブスク」等であたたかく後進を見守る。
幼少時、父の友人のピアノ教師に「10年に1人の逸材」と言われるものの「100年に1人なら責任も感じるけど、、」と「三つ子の魂百まで」を優先し作家を志す。
村林 基彦(1975年12月15日-)
幼少期より「ヤマハ音楽教室」でピアノ、エレクトーンに触れ、高校の部活でサックスを始める。音楽はJazzを筆頭としたインストルメンタル音楽、自作自演のポップス、メタル音楽を好み、読書とゲームに明け暮れる10代を過ごす。物理学を志したが茶農家の祖父母を喜ばすべく受験した名城大学農学部で生物学、化学の面白さに目覚めるも、読書とゲームに明け暮れる。父の税理士独立を機に、大学卒業後は会計・税務の道に進むことを決意するも、大学4年時(1997年5月)に父が他界し、税理士事務所は閉鎖。知り合いの税理士事務所を転々としながら、大学時代にアルバイトで関わった、コンベンション業界でフリーランスとして活動。
2002年夏の税理士試験で法務への不適正を痛感していたところに、コンベンション業界のフリーランス仲間の竹中三四郎の法人化の手伝いを機に、デイブレイクフレーバーの仕事を始める。
エレクトーンでMIDIを知りデスクトップミュージックへ至る過程で、Macをはじめとするコンピューターに触れる機会も多く、コンベンションのデジタル化にあわせて、WEBアプリケーションを独学で試行錯誤しながら作成して現在に至る。